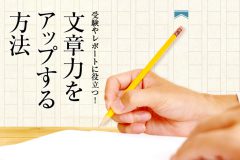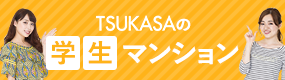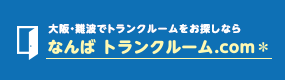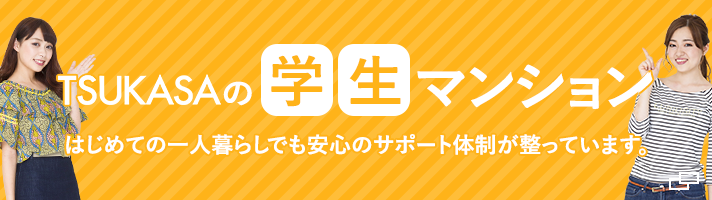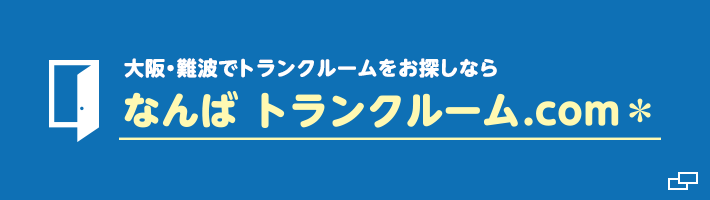みなさんは「ことわざ」をどのくらい知っていますか?
大学入試の現代文には、ことわざや四字熟語などの問題が出る大学もあります。
意外と見落としがちな分野ですが、一度ざっと見ておくと点数の取りこぼしがなくなりますよ!
今回は知っておくと差がつくことわざを一気にご紹介します。
爾汝(じじょ)の交わり
相手を遠慮なく呼び合えるほどの親密な間柄であること。
車を借る者は之を馳せ、衣を借るものは之を破る。
車でも衣服でも、人から借りたものは扱いが乱暴になりがちである。
鞍掛馬(くらかけうま)の稽古
木馬の上で練習しても乗馬がうまくならないように、どんなに知識があっても実際に役立たなければ価値がない。
画餅(がべい)に帰す
考えたことが役に立たずむだになること。
虚仮(こけ)の後思案
愚かな人は肝心な時に良案が出ず、その後にどうでもいい考えが浮かぶものだ。
一文銭で生爪剥がす
わずかなお金を出さなくて自分の身が傷ついても何の後悔もないこと。
煩悩あれば菩提あり
煩悩と菩提は表裏一体であり、迷いがあるから悟りを開くこともあること。
香餌(こうじ)の下必ず死魚あり
よいにおいの餌の下には死んだ魚がかかっているように、利益の裏には危険が潜んでいること。
騎虎(きこ)の勢い
虎に乗った者は途中で降りると危険なので降りられないように、一度始めたことが途中でやめられなくなること。
灸を据える
きつくこらしめ、戒めること。
亀の年を鶴がうらやむ
1000年生きられると言われる鶴も万年の寿命を持つと言われる亀をうらやむように、欲には限りがないことのたとえ。
枯れ木も山のにぎわい
つまらないものでもないよりはマシである。
嘉肴(かこう)ありといえども食らわずんばその旨きを知らず
何事も自分で体験しなければその値打ちやよさは分からない。
たくあんのおもしに茶袋
たくあんのおもしに軽い茶袋を使っても無意味である=効き目のないこと。
魯魚(ろぎょ)の誤り
文字のつくりが似ていて書き間違えること。
逸物の鷹も放さねば捕らず
優秀な鷹でも空に放たなければ狩ができないように、能力がある者でも力を十分に発揮せねば何の役にも立たない。
幽明(ゆうめい)境を異にする
死に別れること。
蚊虻(ぶんぼう)牛羊を走らす
蚊やアブのような小さな虫が集まれば、馬や羊のような大きな動物もかゆさで走りだすように、弱小のものでも大きなものを動かすことができる。
白駒の隙(げき)を過ぐるがごとし
白い馬が壁の隙間をあっという間に過ぎ去るように、月日が過ぎるのが早いということ。
家貧しくして孝子あらわる
いえが貧乏だと子が親孝行をして助けることから、苦境に立った時は助けるものが現れること。
好事魔多し
よいことは邪魔が入りやすい。
巧詐は拙誠に如かず
人間関係をよく保つためには、上手に誤魔化すより拙い方法でも誠意を持って行う方が良い。
みなさんはいくつ知っていましたか?
難しいものもありますが、知っておくと日常生活でも役立つこと間違いなしです。
現代文の読解に加えて、ことわざも一般常識として勉強しておきましょう。